〒395-0051 長野県飯田市高羽町2丁目5番地10(飯田駅から徒歩5分、車2分 駐車場:あり)
受付時間
定休日:原則 日曜日、祝日
遺言書作成支援
遺言の基礎
遺言には、次の3種類があります。 下記のほかに特別方式の遺言(死亡が迫った場合等)がありますが、ここでは割愛します。)
1,自筆証書遺言 自筆証書遺言 とはどういうものなのか 文字どおり全文を自書し、 日付け、署名、押印したものを言います。 ① その遺言が遺言しようとしている人の手によって書かれたものであることが要件です。 人に書いてもらったものや、手を添えてもらったもの、パソコンなどで印字したもの、ビデオメッセージなども、ダメです。 但し法律が改正されて、財産を示す書面に関しては、一定の要件(※1)を満たす限り、パソコンで作成したものや、人に作成してもらったものでも、有効とされています。 日付けの無いものについては、遺言書が無効とされたケースもあります。 それは、遺言書は、遺言者が何度でも書き換えることができます。その際、日付けがない遺言書が何枚もでてきた場合には、遺言者の最終の意思が確認できないからなのです。
※1 財産を示す書面に関する一定の条件とは 遺言書には、相続人ごとに財産を特定しなければなりません。その財産の種類が多い場合には、別紙に書くことができます。これを「財産目録」といいます。この財産目録については、パソコンで作成したものや人に書いてもらったものでも構いませんが、次の形式があります
① 全ページに「遺言者が署名・押印をする」
② 全ページに「ページ数を入れる」 例 1/3 2/3 3/3 (3枚中1枚目、2枚目、3枚目)
2、公正証書遺言
公正証書遺言とはどんなものなのか:公証人の作成する公正証書によってする遺言を言います。 遺言者が公証人の前で遺言の趣旨を述べ、公証人がこれを公正証書にした遺言です。方式としては、証人2人以上の立会があること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に直接口授すること、公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ。その後、遺言者及び証人が筆記の正確であることを確認の上、各自署名押印する。 〇 遺言者が署名できないとき:公証人がその理由を付記して、署名に代えるできます。 〇 口のきけない人、耳の聞こえない人の場合:手話や筆談によって公正証書遺言ができます。 〇 公正証書は、法律の専門家である「公証人」が作成するので、方式不備による、遺言書の無効ということはありません。 〇 公証人の手数料がかかる。 公証人は法務大臣が任命する国家公務員ですが、その収入は手数料で賄われるため、(公証人手数料令)公証人の手数料が必要になります。
〇 証人について:上記でも述べましたが、公正証書遺言の場合、証人2人以上必要です。 証人になれない人:① 未成年者 ② 推定相続人(相続人が配偶者と子のときは、配偶者及び子は証人になれません)③ 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記及び雇人 ④ 署名することができない人(証人として署名するので)
〇 公証人との打ち合わせは、代理人として「委任状」を頂ければ、行政書士が行うことができます。 〇 公正証書の最大のメリットとしては、(公正証書に限ったことではありませんが)遺言書があれば、遺言書で指定された人に、直ちに財産の移転ができます。遺言書がない場合には、相続人全員の戸籍謄本類、住民票、印鑑証明書等多くの手間、時間、お金が必要となります。
3、秘密証書遺言 余り利用されていませんが、「秘密証書遺言」というものがあります。 秘密証書遺言とは:遺言書が遺言の内容を秘密にしたいが、その存在だけは明らかにしたいときに場合に作成されまあす。 秘密証書遺言の要件
① 秘密証書遺言は、自筆でも、タイプやパソコンでも作成できます。
② 遺言者が、その遺言書に署名し、印を押します。
③ 遺言者が、その遺言書を封じ、証書に用いた印鑑をもって封印すること
④ 遺言者が、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自分の遺言者であること並びに筆者の氏名及 び住所を申述すること
⑤ 公証人に、その遺言者を提出して日付けおよび遺言者の申述を封紙に記載して、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すことで完成です。
〇 秘密証書遺言のデメリット
① 公証役場に保管されません。従って紛失、破棄、隠匿、改変等の問題が発生する可能性もあります。
② 公証人及び証人がその証書を見ていないばかりか、何ら関与していませんので、内容不備、内容の不明確で遺言書が無効になる可能性があります。
4、遺留分について ① 遺留分は、被相続人の親族が、相続に 関して法律上取得することを保証されている一定の割合のことをいいます。 ② 留分権利者:被相続人の配偶者、子、直系尊属であり、法定相続人でも、兄弟姉妹には認められていません。③ 遺留分の割合:各相続人の割合は、直系尊属だけが相続人であるときは、遺産の3分の1、その他の時は、2分に1です。 ④ 各相続人の具体的な遺留分の割合に、法定相続分を乗じたものになります。 例 配偶者と子供2人の場合の遺留分の割合 〇 配偶者:遺留分2分の1×法定相続分2分の1=遺産の4分の1 〇 子1人:遺留分2分の1×(法定相続分2分の1×2分の1)=遺産の8分の1 となります。 ⑤ 遺留分を侵害する遺言書であっても、当然には無効とならず、遺留分を侵害された遺留分権利者に、「遺留分減殺請求権を認め」これを侵害する贈与や遺贈を取り戻す道が開かれています。
自筆証書遺言書保管制度
制度の概要 自筆証書遺言を作成した人が、法務局に遺言書の保管の申請をすることができる制度ができました。保管制度を利用することにより、遺言者や相続人、受遺者にもメリットがあります。
(1)遺言者のメリット ① 自宅等で保管すると紛失の恐れがあるが、法務局で保管してくれるので安心 ② 遺言者の死亡後、発見されないことがある。 ③ 他人に見つかった場合、かってに改ざんされてしまう恐れがある。 ④ 他人に見つかった場合、破棄されたり、隠匿される恐れがある。 〇 上記のような事態が避けられる。
(2) 相続人・受遺者のメリット ① 遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きは不要 ② 「遺言書保管事実証明書」の交付請求ができる ③ 「遺言書の閲覧請求」ができる 〇 相続人、受遺者は、上記のように遺言者の存在を確認することができる(ただし、遺言者が死亡してから)
(3)保管申請の流れ ① 遺言者が、自筆証書遺言書を作成する。(上記参照) ② 保管申請する保管所を決める。 〇 保管申請ができる遺言書保管所 遺言書の住所地、遺言者の本籍地、遺言者の不動産の所在地のいづれか ③ 申請書を作成する ④ 保管申請の予約をする。(必ず前もって法務局に予約の電話を入れて、申請日を予約する) ⑤ 予約した日時に、申請書、添付書類、手数料を持参して申請する。 〇 申請するには、次の書類を用意して申請する 一、自筆証書遺言書 ホッチキス止めはしない。封筒は不要 二、申請書 あらかじめ作成して行く 三、添付書類 本籍地記載のある住民票の写し等(3か月以内のもの) 四、本人確認資料(次のうち1点)マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書等 五、手数料 遺言書保管の手数料は、1通につき3,900円です。 ⑥ 保管証を受け取る。
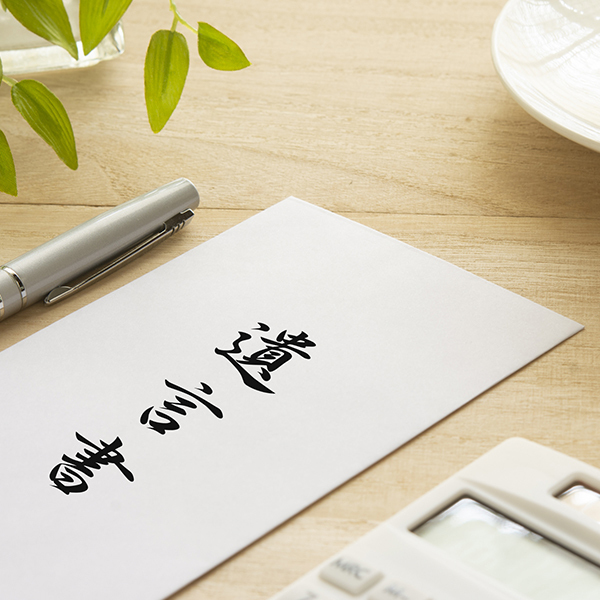
( 4 ) 遺言者の閲覧
① 遺言者は、預けた遺言書を見ることができます(遺言書の閲覧) ② 遺言者は、預けた遺言書を返してもらう(遺言の撤回) ③ 遺言者は、変更事項を届け出ることができます。(変更の届出) ④ 相続人等は、遺言書が預けられているのか確認する。(証明書の請求) ⑤ 相続人等は、遺言書の内容等の証明書の請求できます。 ⑥ 相続人等は、遺言書の閲覧ができます。
※ ただし、上記の④~⑥までの請求は、遺言者が亡くなっている場合に限られます。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
原則 9:00~18:00
<定休日>
原則 日曜日、祝日
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
行政書士
あすなろ法務事務所

住所
〒395-0051 長野県飯田市高羽町2丁目5番地10
アクセス
飯田駅から徒歩5分、車2分
駐車場:あり
受付時間
原則 9:00~18:00
定休日
原則 日曜日、祝日

